こんにちは!「Hug Rush」ブログのハルです!
自然災害時に関わらず、私たちは日常生活において、予期せぬ事故や急病に遭遇することは珍しくありません。そのような緊急時に適切な対応ができるかどうかが、時として命を左右する重要な分かれ目となります。
心肺蘇生法を学ぶことで、家族や友人、さらには誰かの大切な人の命を救う可能性を大いに秘めています。今日学ぶことが、いつか誰かの命を救うきっかけになるかもしれません。
本記事では、心肺蘇生法(CPR)について、わかりやすく解説していきます。命を救う知識を一緒に学んでいきましょう。
心肺蘇生法(CPR)

心肺蘇生法って、ぼくたち一般人でもやらなきゃいけないのかな?

いかに早く救命処置を行うかで、救命率が大きく変わってくるんだよ。
一般市民による心肺蘇生法の必要性
急病人や事故の現場に居合わせた人のことを「バイスタンダー」といいます。
バイスタンダーによる適切な初期対応は、傷病者の生存率と社会復帰率を大きく向上させる可能性があるため、非常に重要な役割を担っています。
救急車の現場到着時間は、現在、全国平均で約10分となっています。
心肺停止状態から1分処置が遅れるごとに約10%生存率が下がり、10分間なにもしなかった場合の生存率は20%を下回るとされています。つまり、救急車が到着するまでに何も処置がされなければ、救命できる可能性は限りなく低くなってしまします。
しかし、バイスタンダーによるCPRは、救命率を約3倍に増やすことができるとされています。
救急隊や医師を待っていては命を救うことはできません。 突然の心停止を救うことができるのは、その場に居合わせた「あなた」しかいません。
あなたが今、そこにいることで、誰かの命を救うことができるのです。
心臓マッサージの必要性
普段、心臓はポンプの役割をしており、体中に血液を送っています。また、血液には酸素が含まれており、体中に酸素を循環させる役割を担っています。
心臓が停止した場合、数秒で意識を失い、酸素の供給が途絶え、数分で脳をはじめとした全身の細胞が死んでしまいます。
心臓が停止したの際に、心臓のポンプ機能を人工的に補助し、脳や重要な臓器などへの酸素供給を維持することで、生存率を高めることができます。
突然死の発生リスク

必要性はわかったけど、そんな場面に遭遇することなんてあるのかな?

日本では年間約9万人もの人が、心臓が原因の突然死で亡くなっているの。
日本では毎日多くの人が心臓を原因とした突然死で命を失っています。
突然死における全体の正確な発生件数は公表されていませんが、心臓が原因で突然心停止となる人だけでも、なんと1年間で約9.1万人。一日に約250人、1時間に約10人(6分に1人)の方が亡くなっています。
また、突然死は高齢者に限らず、高校生以下でも、交通事故や熱中症などの死亡を除く突然死が、毎年全国で約40件も発生しています。これは、男子の割合が圧倒的に多く、運動中の突然死が約50%、運動直後が約15%を占めています。
突然死の原因
突然死の原因としてもっとも多いのが心臓疾患で約60%を占めます。
次に多いのが脳疾患で、ほかにも大動脈疾患や呼吸器疾患などがあります。
これらの疾患は血液が原因とも言われており、生活習慣をあらためることで発生リスクを減らすことが可能です。
主なリスク要因として、以下のものが挙げられます。
- 高血圧
- 糖尿病
- 肥満
- 喫煙
- 運動不足
- 過多なアルコール摂取
まずは食生活を見直し、適度な運動を心がけましょう。また、定期的に健康診断を受診することをおすすめします。
[ 心肺蘇生法 ] 命を守る6つの基本テクニック
心肺蘇生法は、心臓や呼吸が止まった人の命を救うための緊急処置です。
主な手順は以下の通りです。わかりやすく解説していきますので、しっかり学んでいきましょう。
1 周囲の安全確認
応急処置を行う際は、周囲の安全確認が非常に重要です。屋外では落下物や車の通行に注意が必要です。一方、屋内では異臭などの臭気に気をつけましょう。特に寒い季節は注意が必要で、ストーブの不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、寒さのために換気扇を使用せずに長時間ガスを使用した調理による酸素欠乏状態などのリスクがあります。
これらは五感で感じることが難しい場合もあるため、周囲の状況を慎重に確認し、自分自身や他者が危険にさらされていないか十分に注意を払うことが大切です。環境に応じた適切な安全確認を行うことで、効果的かつ安全な応急処置が可能となります。
2 反応の確認
傷病者の反応を確認する際は、まず小さな声で弱く肩を叩き、徐々に声を大きくし、叩く力も強めていきます。反応なしと判断するには慎重さが必要で、確信が得られない場合は適度な痛み刺激を与えて確認することが有効です。例えば、胸の真ん中を指の骨で押さえつけたり、ペンなどの固いもので指の爪を押さえつけたりする方法があります。
また、新生児や乳児などは足の裏を刺激しながら呼びかけます。目を開ける、応答する、泣くなどの仕草があれば「反応あり」と判断し、これらの反応がない場合は「反応なし」と判断します。
3 助けを呼ぶ
反応がない場合はすぐに助けを呼び、119番通報とAEDを手配します。
この段階で詳細な容態はわかりませんが、重篤な状態である可能性が高いため、一刻も早く助けを呼びましょう。
駆けつけた人が複数人いる場合、特に日本人は引っ込み思案な方が多い特性があるため、協力を得るには個人を指名して明確に依頼してください。例えば、「青いシャツの男性、あなたは119番に電話してください」のように、特徴を捉えて具体的に指示することで、確実な対応が期待できます。

もし誰もいなかったらどうすればいいの?

まずは119番通報を優先しましょう。スピーカーモードを活用すると便利です。
AEDはすぐ近くにある場合のみ取りに行きましょう。
※119番通報について詳しい説明は、以下の記事をご覧ください。
4 呼吸の確認
10秒以内に傷病者の胸と腹部の動きを見て、普段通りの呼吸をしているか確認します。
呼吸の確認は10秒以内で行いますが、しっかりと時間をかけて確認しましょう。通常、成人であれば、約4秒に1回の呼吸をしています。小児以下であれば約2秒に1回の呼吸をしています。
呼吸の有無を判断する最も効果的な方法は、胸や腹部の動きを観察することです。特に寒い季節には、厚着をしている場合が多いため、必要に応じて衣服の一部をめくるなどして、正確に呼吸の動きを確認することが重要です。
また、心停止直後に見られる呼吸として、死戦期呼吸があります。一見すると呼吸しているように見えますが、実際には生命維持に必要な有効な呼吸ではありませんので、呼吸なしと判断します。
呼吸がない場合又は判断に迷った場合は、勇気を持って心肺蘇生法(CPR)を実施しましょう。
※死戦期呼吸の特徴
・しゃくりあげるような、あるいはあえぐような不規則な呼吸
・下顎の動きや口をパクパクさせる動作
・胸郭の動きがほとんどない
・毎分数回程度の徐呼吸で、呼吸の間隔が徐々に長くなる
5 胸骨圧迫(心臓マッサージ)
胸骨圧迫は心臓機能の回復を目指すとともに、それが実現するまでの間、体内での酸素の循環を維持する役割を果たしています。このように、胸骨圧迫は心肺蘇生法の中で最も重要な技術であり、適切に実施することで生存率を大きく向上させることができます。
胸骨圧迫の手順は、以下のとおりです。
○救急処置を行う際、傷病者の口にハンカチやタオルなどを軽く被せることをお勧めします。これは、
胸骨圧迫などの反動で傷病者が嘔吐する場合があるからです。また、農薬などの有害物質を飲んでい
る可能性も考慮する必要があり、口から有害なガスが排出されたりする可能性があるためです。
○傷病者を硬い床面などに仰向けに寝かせ、胸の真ん中に手の平の付け根部分を当て、傷病者に対して
垂直に圧迫します。
・成人の場合は、胸の真ん中を、深さ約5cm、1分間に100~120回のテンポで圧迫します。
・小児や極端に細身の高齢者の方などは、胸の厚さの約3分の1の深さで圧迫します。
※ポンプ機能を最大限に実施するには、圧迫と同様に元の位置まで戻す解除も重要です。
○救急隊の到着又は傷病者に反応が現れるまで、胸骨圧迫と人工呼吸のサイクルを継続します。
・移動の場合など中断時間は10秒以内とし、極力中断時間を短くします。
・救助者が2名以上いる場合は、2分を目安に胸骨圧迫を交代しましょう。胸骨圧迫の質は体力の消
耗に伴い、時間の経過とともに低下する傾向があり、特に2分を過ぎると顕著になることが示されて
います。これは、アスリートなど体力に自信のある人でも例外ではありません。
・周囲の人は胸骨圧迫のテンポ、圧迫・解除、角度などを観察し、助言するなどのサポートをしまし
ょう。
○AEDが到着したら電源を入れ、指示に従います。電極パッドを貼り、解析結果に従ってショックを実
施します。

あれっ?人工呼吸は必要ないの?

必ず実施しないといけないわけではないんだよ。状況に応じた判断が必要なの。
6 人工呼吸
一般的な成人の心停止の場合、人工呼吸を省略し、胸骨圧迫とAEDによる電気ショックのみを実施することが認められています。
これには以下の3つの理由があります。
- もともと呼吸をしっかりされていた方であれば、血液中に酸素を十分含んでいるため、胸骨圧迫のみでも酸素を循環させることができる
- 感染症のリスクや嘔吐、出血の可能性もある
- 技術が必要であるため、
また、誰しも人工呼吸を実施するのは抵抗があるのではないでしょうか。それが見ず知らずの方であればなおさらです。また、感染症などのリスクや嘔吐、出血がある場合もあります。これは、救命のハードルを下げ、より多くの人が躊躇なく心肺蘇生を行えるようにするためです。
過失などによる罰則について

骨が折れたりしたらどうしよう、、、間違ったやり方で悪化しないか心配だなぁ、、、

骨折は治るけど、なにもしなければ助からないよ!
助けようとして過って悪化させた場合、罪に問われることはないんだよ。
一般人が善意で心肺蘇生法を実施した場合、過失が生じても罰則を受けることはほとんどありません。以下に主な理由を説明します:
- 法的保護:
民法上、心肺蘇生法は「緊急事務管理」に該当し、悪意または重過失がない限り、実施者が責任を問われることはありません5. これは、一般市民によるAED使用も含めて適用されます. - 刑法上の考慮:
救命手当実施者に要求される注意義務の程度は医師よりも低く設定されており、その注意義務を尽くしていれば過失犯は成立しません5. - 公的見解:
1994年に総務庁から発表された報告書では、市民が行った心肺蘇生処置について、民事上も刑事上も責任を問われることはまずないと明確に述べられています1. - 救命促進の観点:
救助の義務がない市民に対して法的責任を問うことは、善意の救助行為を抑制してしまう可能性があるため、避けられています3. - AEDの安全性:
AEDは機械の指示に従って使用すれば、一般人が失敗する可能性は極めて低いとされています5.
ただし、「悪意」で行動した場合、つまり結果が予測できるにもかかわらずあえて行動した場合には、責任を問われる可能性があります1. しかし、これは通常の善意の救命行為には当てはまりません.
結論として、一般人が善意で心肺蘇生法を実施した場合、たとえ過失があったとしても、法的責任を問われることはほとんどないと考えてよいでしょう.

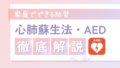
コメント